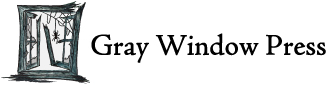Gray Window Pressで最初の本を出したのは2019年の春だ。Debacle Path vol.1を3月に、その2ヶ月後にはMDC本を出版したので、あの頃は今思えば本当にアホみたいに(賃労請け仕事も含め)連日15時間くらい作業していて眼精疲労になったりしたのだが、ことMDC本については、当初はどれだけ売れるのかまったくわからず、個人でパンクのジンを作っている友人にそれとなく訊いてみたものの、「300冊売れればいいほうじゃない?」とすら言われたので、そんなに売れないものなのか…と、少しがっかりしながらその部数を決めかねていた。ものづくりは何でもだいたいそうだが、作る数が少なければ単価は上がる。で結局見積もりを何パターンか取って、500も1000もそんなに変わらんじゃないかと思い(変わらないことはないのだが)、えいやと1000部刷った。
2019年の売上表を見ると、出版直後の6月末にMDCが再来日したこともあって最初はよく売れ(招聘した中野Moonstepのナオキさんの尽力で、デイヴ・ディクターによる朗読イベントをやってもらえたのも大きい)、あと8月の頭にVHS MAGにデイヴ・ディクターのインタビューが載ったことで注文が結構入ったのだが、9月に入るとそれもピタッと止まってしまい、これはどうしたものか…と貸倉庫に保管してある在庫を前に頭を抱えていた。勢いで始めた個人出版、すべて手探りでやっており、「同業」の友人などもおらず、調子に乗ってバーコードなどもつけてしまったので、書店への流通、取次というまったく未知の世界にも関わることになった。販売職なんて、昔デスメタルやブラックメタルのCDを売る潰れかけのレコード屋でバイトしかしたことがない私でも、出版社による書店への営業が存在する、ということはなんとなくは知ってはいたが、当時書店への営業は、ジュンク堂、丸善、三省堂などのようなチェーン店の、しかも大型店舗に注文案内をFAXするのみで(在庫数の多い店舗ならシレッと自主出版ものも入れてくれないだろうか、という淡い期待を抱いてのことである)、これはちょっと実際に、いわゆる「営業」というものをやった方がいいのだろうかと思い始め、というかその思いに完全に囚われ、作戦を立てた。ちなみに過去に営業職をやったことはない。
町に残っている個人店などは置いてもらったとしても売れずに返品されるのが関の山なのでそもそも除外し、ターゲットは地方や東京のそんなにメジャーでない街の駅ビルなどに入っているチェーン書店に決めた。注文案内をプリントアウトしたA4用紙と名刺をにぎりしめ、訪れた土地土地にあるお店に緊張をもって入り、まずは音楽の棚にMDC本が置かれていないかを確認する。置いてあるわけがない。さて、意を決し、品出しをしている店員やレジの人に声をかけて、「音楽や芸術の本の担当の方はいらっしゃいますか?」と切り出す。そんな具体的な担当が各店舗にいるのかは知らない。が、ここで担当者に引き継がれたことは一度もなく、やっぱり門前払いかな?!と悲しくなる。「担当に伝えますので…」という対応をされたことがほとんどであり、小汚いロン毛から、ハードコア・パンクなどというよくわからない音楽の本の説明を突然されたそういう書店員さんたちの反応は、どれも「はあ…」という感じだった。紙と名刺は担当者に渡ったのだろうか、それもわからない。そんなわけで、苦手な営業頑張ったぞ!という勝手な満足感は少しだけ得られたものの、それが注文につながった様子はなかった。大失敗。
そんな中、翌年になるとにわかに新型コロナ禍が始まり(アナキストの水田ふうさんが入院し、その病院に何度か伺った時期だったこともあり、この病禍の始まりの状況はよく覚えている)、あっという間に人との接触が極端に制限される世の中になってしまったので、もはや飛び込み営業どころではなくなり、最初の「緊急事態宣言」下の4月末にDebacle Path vol.2を出したら、残っていたMDC本も一緒にまた動き始め、オンライン書店等でもそこそこ売れ、結局その夏には版元品切れとなった。1800円の本を1000冊捌くのに14ヶ月だから、まあ自主出版としては上出来だと言えるのだろう(ちなみにそのDebacle Path vol.2は昨年の10月にようやく品切れ、800冊捌くのに4年半かかった)。たださすがに増刷するほどではないだろうと思い、その後もずっと品切れの状態で、今も多少プレミアがついた値段で古書が売られているのを見るが、全国の図書館にも結構入れてもらえたし、まあこのままでいいかと思っている。今同じものを例えば300冊だけ刷ったら売価は倍近くになってしまうだろうから、経理的に増刷はムリ、ということでもあるのだが。紙の値段もこの5年で非常に上がった。
こういった個人出版、と言っても一応バーコードをつけて取次による流通も行っている微妙な規模のものは、書店への営業をどうするべきなのだろうか。注文分しか発注しない、できないので、当然その本の存在を書店担当者等にまず知ってもらうことが鍵となる。いやしかし、Gray Window Pressは今のところ、ハードコア・パンクに特化した本ばかりを出しており、そもそもその本を「外」へ広めることも考えていないので(つまり読者は極めて限られているので)、営業自体が必要ないのだろうか。しかもそのほとんどはパンクや自主制作専門のレコード店や、模索舎のような特殊な独立系書店で売れる。あとはネット本屋やAmazonなど。でもそれだけだとどうしても売れ残る。だから少しは「外」にアピールもしないといけない。以前「近代出版研究 2023 第2号」に載っていた「版元営業はどのような仕事か」(平林緑萌)という記事を読んで、先述のようにただ闇雲に書店に飛び込んでは適当な店員に声をかけて営業した気になっていた私は身がすくむ思いだったが、出版社内にそういう営業職が存在しているということは、やはりそれは個人出版の規模であろうが、1冊でも多く売るために、営業のマネゴトをしたほうがいいのだろうか。それにしては売れる見込みに対しての労力が大きすぎる気もする。もういっそのことバーコードをつけるのをやめようか、直販とレコード屋と興味を持ってくれているいくつかの個人書店だけで十分なのではないのか。営業といったいらないことは考えず、粛々と本を作ればいいのではないか……。
というようなことを、先日パートナーに連れられて行った名古屋の某独立系書店の棚に当出版の本が並んでいないことを確認して、あれこれと店内で思いを巡らせた。リベラル系の本を多く置く書店だったが、『パンクの系譜学』は未だ平積みしてある一方で、おそらくこの書店にはDebacle Path 別冊2の存在を知られていないのであろう、該冊子は見当たらなかった。架棚にはフェミニズム関係の本も多くあったが、その中に『スピットボーイのルール』はなかった。これはやはり千載一遇の営業のチャンスなのか! いやしかし、まあ誰もウチの本はこのお店で買わないだろう…、と根が控えめにできている私は勝手に諦めモードになり、そのまま店を出た。
(2025.2.2)