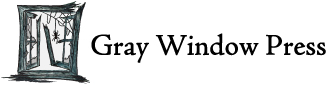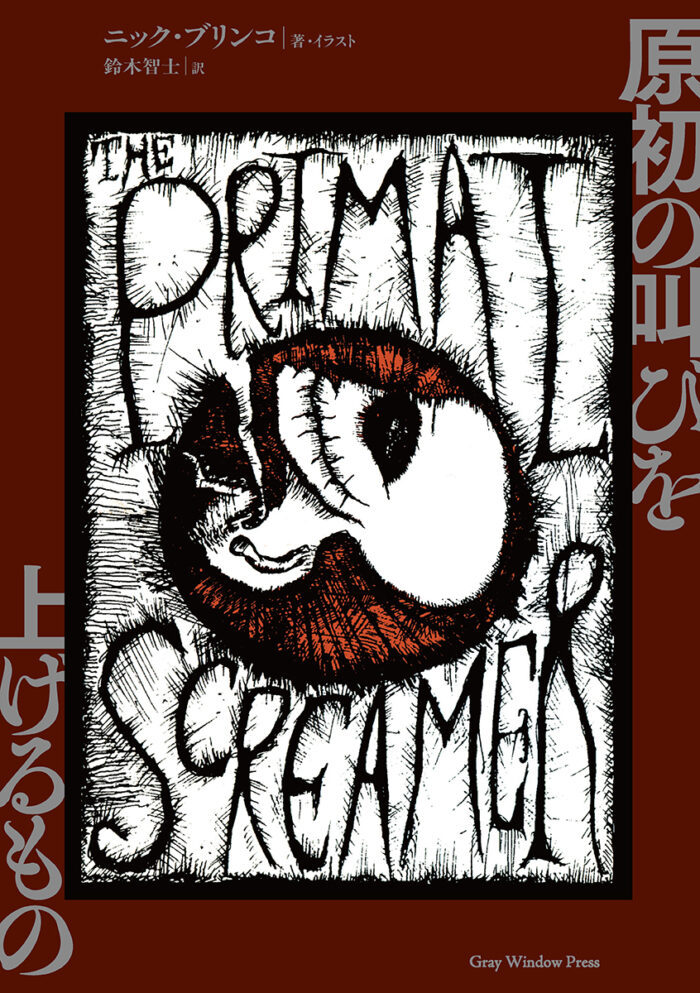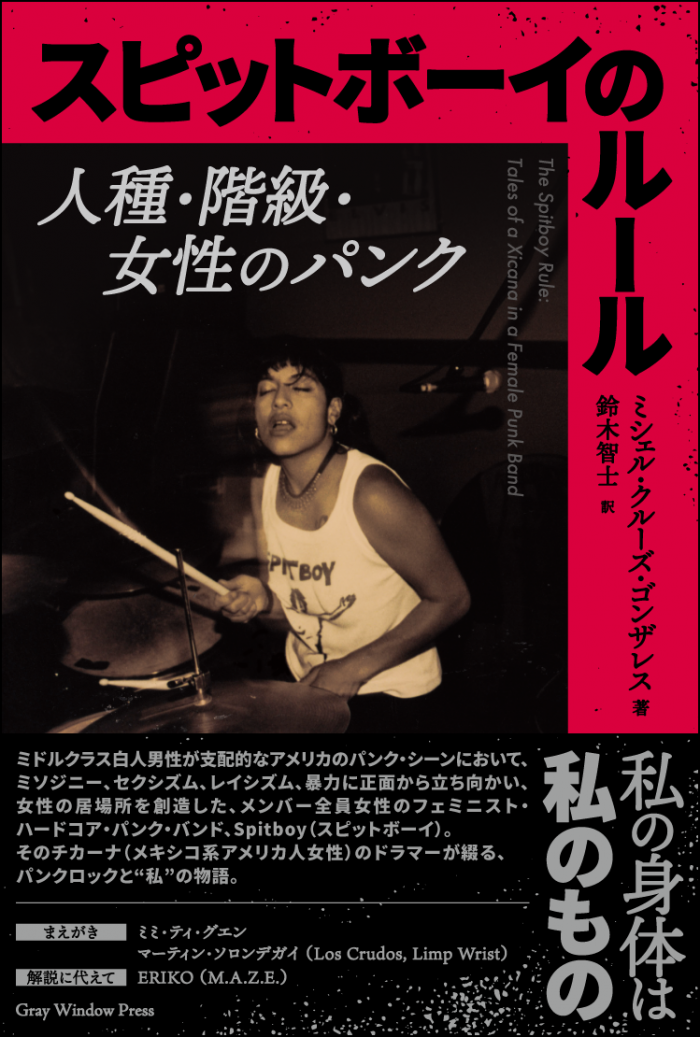2025年もお世話になりました。
楠間あゆ Closh Terroreye 新井一三 A・K・アコスタ 鈴木智士
楠間あゆ
音楽・Black Star Musical Club & Lucky Star Musical Club Nyota: Classic Taarab Recordings from Tanga VIDEO
・Outgrow Madness【Live】「われらの狂気を生き延びる道を教えよ Vol.2」@東高円寺二万電圧(2025年7月12日)
映画
続きを読む →