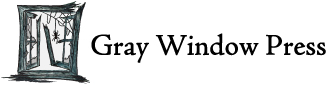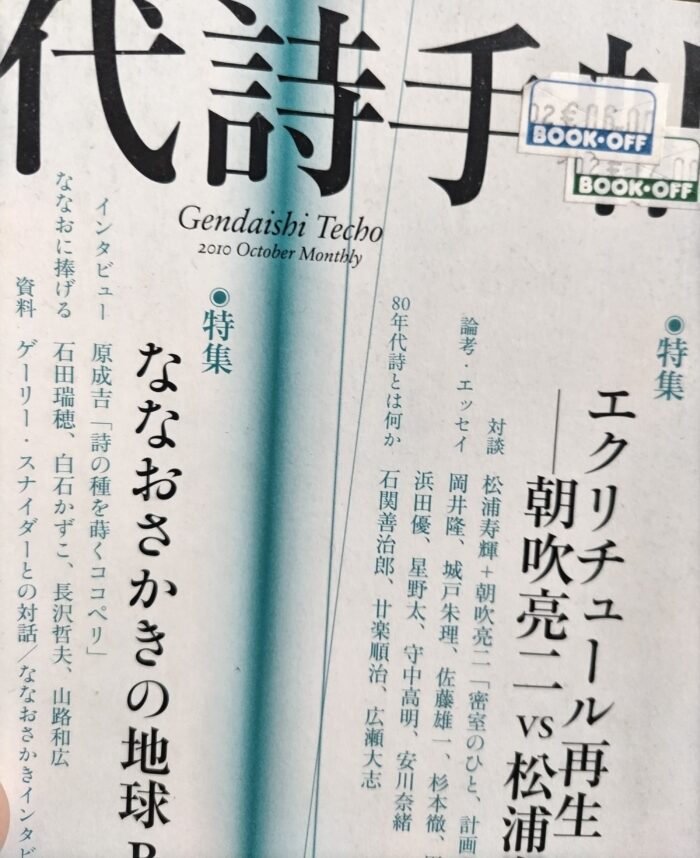
古書を買っていると、古いレシートや私物っぽい栞、新聞の切り抜き、メモ、さらには手紙などが本の間に挟まっていることがたまにあるが、それが元々は誰かへの献本だったときには、献本の短冊や挨拶状などが入っていることもある。まあそれらはおまけみたいなもので、入ってたらちょっと得した気分にもなるのだが、中にはえらく情報量の多いおまけとなるものもある。
2011年の震災後に日本にいるのが嫌になり、翌年に半年くらい、主にヨーロッパのパンクスを尋ねてブラブラしていたことは以前のブログで書いていたが(その旅行記として該ブログを始めたのだった)、友人Tが運営していたそのサーバーが死んでしまい、そのブログの内容も大半が消えてしまった。そのことは未だに少し恨んでいる。データが残っていたもののいくつかはこのブログに再掲してある。今回の話は昔書いた内容と重複するかもしれない。
その洋行が4ヶ月ほど経ったころの9月初めだったか、ちょうどこれも日本での生活に嫌気がさしていた愚妹が、社会人生活で貯め込んだ私費を投じ、「留学」と称してフランスのパリに住み始めたために、そこに行けば宿代がかからないというセコい考えで、ひと月ほど泊めてもらったことがあった。貧乏旅行で一番金を使うのは、やはり毎日の宿代である。毎月の家賃と一緒だ。だからなるべく友人や、紹介してもらった友人の友人の家、スクワットなどにお世話になっていたが、そう常にこちらの都合よく泊めてもらえるわけでもないので、そういうときは適当な安ドミトリーに泊まるのだが、ドミトリーは疲れる。その話は前回少し書いた。うるさい酒浸り白人若者旅行者集団と同室になったときはとても迷惑だし、ベルリンの定宿であったほとんど刑務所のような巨大ドミトリーは、ただ安いだけで雰囲気も設備も最悪だった。
フランス語はまったくできないし、特段パリに興味があったわけでもなく、だからと言って、辻潤のように日本からわざわざ持っていった『大菩薩峠』をただ読んで過ごそうとしたわけでは当然ないが、滞在時にちょうどやっていたL’Etrange Festivalという映画祭に通う(ケネス・アンガー御大のトークやTechnicolor Skullでのテルミン・パフォーマンスを観たのもこの映画祭だ)以外は、セーヌ川沿いを散歩をしたり、美術館に行ったりと、ごく普通の旅行者のようにふるまっていた。パリには知り合いのパンクスもいなかった。妹のところで荷物が軽くなったおかげで、その間にロンドンに一週間ほど行ったり、妹と一緒にワルシャワまで飛んで、そこからバスを乗り継ぎクラクフやアウシュビッツにも行った。
さて、パリのオペラ地区にブックオフがあると妹に聞いたのだったか、暇な身なのである日覗いてみた。ほとんど日本のブックオフと変わらない店内の様子に驚いたが(あの独特の臭いはしなかったが)、会計まで日本語だったのにはやや興をそがれた。そこでは暇つぶしにと、わりと直近の「映画芸術」を数号と、均一棚にあった兵藤正之助の新書『坂口安吾』、アラン・ムーアの『フロム・ヘル』日本語版の上巻が、なぜか2ユーロ(当時のレートで200円くらい。2012年はかなりの円高だった)で売られていたので、ちょっとデカいなと思いながらもそれらを買い、ポルト・ドーフィヌとユゴー駅の間くらいにあった妹宅に戻ってパラパラとめくっていた。すると「映画芸術」436号には手紙が挟まれており、それは「安川奈緒」という方に宛てたものであった。寄稿に対するお礼状のようなものである。どんな人なのだろうと思い、該誌に掲載の記事を読んでみると、それは私の苦手な映画監督、河瀨直美が震災後に制作したという、ビクトル・エリセやアピチャッポンなども参加した、「3分11秒」のオムニバス映画に対する、なかなか辛辣な批評であった(詳細はそれを読んでもらいたいが、「震災」の起きた3月11日と3分11秒の間には何の関係もないのに、1年かそこら経っただけで、すでにその天災が「記号」として消費されていること、また映画の最初の「奉納上映」が、河瀨の地元の奈良で行われたことは、福島とは何の関係もないことへの違和感の表明のような文章である)。安川氏の記名の下には「詩人」とあったのだが、詩にはほとんど興味のない私はその人のことをまったく知らなかったので、さっそくググってみたところ、どうもここ数年はパリに住まれていて、しかも驚くことに、その年の7月、つまりこれを手にした約二ヶ月前に、若くしてこの地で亡くなったという。厭らしいながらも、そんな人物に宛てた献本がパリのブックオフに売られているということは、つまりは遺品が当地で処分されたと考えるのが当然となってくるが、なんだか妙なものを手に入れてしまったようである。
その数日後にまたオペラの近くまで行ったので、再度ブックオフに寄り、野卑ながらも他にも「遺品」がないか、特に1冊だけ出版されているという安川氏の詩集がないものかと棚を見ていたところ、「現代詩手帖」が数冊置いてあり、そこには手紙の類は入っていなかったものの、安川奈緒の詩や論考などが掲載されたものばかりだったので、おそらくそれらもそうだったのだろう。そのうちの1冊だけ購ったが、その巻末には安川氏のパリの住所が載っていた。作家の住所が今も載ってるなんて、詩の世界は往時のままなのか、それともものすごく閉じた世界なのか、いたずらの類は存在する余地のない、とても潔白な世界なのか…。もちろんその住所を知ったからといってどうするわけでもなかったが、その住所を眺めていると、何かその詩人の死が生々しく迫ってくるようでもあった。
で結局のところ、安川奈緒の詩は今日に至ってもネット上でしか読んだことがなく(その出版されている1冊は異様なまでの高額になっているし、その後作品集や論考集のようなものが出た形跡もなさそうだ)、過去の雑誌などを漁るほど現代詩に興味があるわけでもなく、ただ本の処分を進めていたときに、これらのパリで買った雑誌が出てきて、この詩人とパリでの日々のことを思い出したのであった。その後私はパリからテルアビブに飛んだ。そのことは「【実用編】イスラエル入国、出国(2012年版)」に書いてある。
(続く)
(2025/3/3)