重くてぶ厚いハードコア・“パンク”・ジャンキーの物語
【書評】Black Heart Fades Blue vol.1~3/Jerry A. Lang (Rare Bird Books, 2022年)
鈴木智士(Gray Window Press)

Poison Ideaのボーカル、ジェリー・Aの自伝、もしくは解説付きの歌詞集が読めたらどんなに嬉しいだろう……。そんなことを、2019年11月の最後の来日ツアーを見てからしばらく考えていた。新代田Feverで見たそのライブは、バンドとしてもまとまっていてとてもよかった(いい感じにダラダラと「ルイ・ルイ」のカバーをやったりもしていた)。この夜はMCで曲の説明も長めにいくつかあって、 “Alan’s on Fire”について、相手にされない妻子の眼の前で焼身自殺した男の話などには、なぜか感動すらしてしまった。そんな体験がしばらく尾を引いていた中、ジェリー氏(と以降ここでは呼ぶことにする)はすでに自伝を書き終えている、という情報をどこかのポッドキャストで耳にしたのは、確か新型コロナ禍が始まりアメリカの中年パンクYoutuberが増えた2020年の夏ごろだった。そして2022年に全3巻という非英語ネイティブ泣かせの大ボリュームで発売されたのが、“Black Heart Fades Blue”というタイトルの本書である。
3冊合計で600ページを超える、昔のジェリー氏みたいにサイズの大きな自伝だが、誰かにこの本の第一印象を聞かれたら、私は「ウィリアム・バロウズの『ジャンキー』のパンク版」と答えるだろう。冗談ではなく、本当にドラッグ、特にヘロインにまつわる話ばかりなのである。文字通りのハードコア・“パンク”・ジャンキーの物語だ(未読だが、ニッキー・シックスの自伝『ヘロイン・ダイアリーズ』もそのタイトルから察するに、似たような話なのだろうか)。バロウズの『ジャンキー』ばりに、あれこれと絶えず起きるドラッグをめぐるトラブル、自分やまわりのジャンキーの生態、売人たちの話、飲酒も含めて20年くらいシラフでいたことがなかったジェリー氏、そしてドラッグ使用がたたって太り、膿瘍ができ、C型肝炎になり、糖尿も酷く、何度か死にかけ……、などなど、おそらく全体の70%、第2巻にいたってはほぼすべての章に、何らかのドラッグ関連のエピソードが登場すると言ってもいい。パンクに“こういった”側面があることは誰もが知る事実だと思うが、ジェリー氏がここまでのジャンキーだったとは知らなかった。Poison Ideaのドキュメンタリー、“Legacy of Dysfunction”(2017年、日本未公開)でもドラッグの話は当然出てきたが、私はどうやらPIというバンド、さらにはジェリー氏へのドラッグの影響を過小評価しすぎていたようである……。
もちろん本書にはそれ以外のPIの話――当時どういうバンドがいて、どういうバンドと対バンしたとか、シーンの変化とか、自伝本には必ず載るそういったパンク史的情報も、ポートランドでずっとやってきたバンドなので特にポートランドに関連するものはあるにはあるが、この表紙以外にただの一枚も写真やフライヤーが登場しない、文字で埋め尽くされた本書の主題は、ジャンキーであったジェリー氏の生き様である。
ジェリー氏には大酒飲みのアル中というイメージを持つ人も多いと思うが、10歳くらいから常用し始めたというアルコールはドラッグがないときの間に合わせの代替品、もしくは特定のドラッグをさらに消費するためのチェイサー的な役割だったようで、酒に関する問題はドラッグ問題ほど出てこない。本人も文中で認めているので何度でも言うが、本当に、文字通りのジャンキーなのだ。海外ツアー中は、自分のパフォーマンスのためにも、知らない土地でいかにドラッグを手に入れるかが勝負だった、というエピソードも繰り返されるが、どうしてもドラッグが手に入らないときには、ウイスキーなど強い酒でごまかしてライブをやっていたらしい。サントリーの角瓶をラッパ飲みしている写真が印象的な2004年の来日ライブは正にそんな状態だったらしく(ヘロイン中毒治療のために処方される「メサドン」というオピオイド系の鎮痛薬、というか、ほぼヘロインよりちょっと弱いだけの麻薬が何度も登場するのだが、そのメサドン中毒になった状態で国を発ち、ツアー中にメサドン切れを起こしていたらしい)、あまりいいパフォーマンスができなかったことが述懐されている。それを教訓にしたのか、2019年の再来日時にはジェリー氏はドラッグ絶ちに成功していたので、集中したいいパフォーマンスができたそうだ。
93年にPIが一度解散した後、ジェリー氏が当時のパートナーやThee Slayer Hippyとやっていたバンド・Giftのヨーロッパ・ツアーでも似たようなことが起きていて、「ツアー中は毎日ドラッグを探すのが日課」であり、ドイツのどこかの街で、いかにも危険地域といったところにある通称「ヤク中公園」に行って、ギャングみたいな集団から偽物を買わされたりしながら、ボロボロのライブを繰り返してツアーは失敗、バンドも停滞、悪夢のドープシックを経験してシラフに戻ると決意したパートナーとも別れてしまったらしい。
もちろん地元ポートランドでの日常のドラッグ問題にもページはたくさん割かれ、ドラッグを手に入れるために犯罪をしたり、誰かを裏切ったり、PIをドラッグほしさだけのために再結成させたりと、ヒドいエピソードがありのままに語られ、またドラッグ絡みで仲間やまわりの誰かが死んだエピソードは、ジェリー氏の思いとともに記され特に心に残る。第2巻に出てくる「ジャンキーはハイになるためではなく、体調維持のためにドラッグを使う」というジェリー氏の言葉は、バロウズ『ジャンキー』内の、「私は朝、寝床から起き出して、ひげを剃り、朝食を食べるのに麻薬が必要なのです。生き続けるのに麻薬が必要なのです。」(鮎川信夫訳)という、ある登場人物の発言と符号する。『ジャンキー』はバロウズの自伝的小説だが、ジェリー氏のこの自伝も、バロウズに負けないドラッグの物語なのだ。
本書について、ジェリー氏は「赦しと告白と贖罪」がテーマだと記しているが、その中でも自分自身が起こしてきた過去の罪に対して謝るような文章が多い。ドラッグはその最たるもので、ジェリー氏が起こした数々のドラッグ問題をここで詳述することはしないが、いくつか例を挙げれば、PIが始まった頃、家を飛び出して路上生活をしているときに、当時ベースを弾いていたGlennの家の地下に居候させてもらっていたのだが、このGlenn一家が、母、兄夫婦含め全員ヘロイン中毒だったこともあり、「ポートランド・パンクのブラックホール」と呼ぶその部屋でカリギュラばりの乱痴気騒ぎをやりまくったとか、あるときドラッグと酒を食らって野外のライブを見に行っていたら呼吸困難になり、それをマウス・トゥ・マウスの心肺蘇生で助けてくれたのが、後に映画監督として成功したガス・ヴァン・サントだったとか、ドラッグで前後不覚、自分でテーブルに頭をぶつけて昏睡状態になり死にかけたこととか、まあそういうエピソードは本当にいくらでも出てくる。
ただしかし、ジェリー氏はこの自伝において、「自分の話は他の誰も語ることができない」という態度を貫いており、自分以外のこと、機能不全に陥った家庭から逃げてきた若者たちが集合した、「疑似家族」と呼べるバンドのメンバーについては、初期メンバーのGlennやDeanなどについては必要最低限だけ書き、そしてお互いに一番の理解者であり親友であったトム・ロバーツ(Pig Champion)のことだけを、数章にわたり思いを記している。PIは(解散中も含めて)40年近い活動期間を通して30人以上のメンバーがいたが、「ストリートの掟」を知らないメタル系のメンバー(「Thee Slayer Hippyが連れてきた連中」と書いてあった)は、真の仲間意識を感じていなかったからかもしれないが、名前が出てくることは少ない。
そのトム(本書の記述に倣ってPig Championではなくトム(・ロバーツ)と記す)についてだが、この自伝は当初2006年のトムの死で終わる構想だったらしく、現に第3巻のトムの死についての非常にヘヴィな章以降は、世情やソーシャルメディア、ジェントリフィケーションのようなポートランドの変化についてなどのエッセイ的な文章が多くなり、時代も一気に進む。トムの死についてはここでは深入りしないが、すでに自分を語ることができない親友に代わり、ジェリー氏はトムについて、非常にありのままで、温もりのある言葉を綴っている。それはジェリー氏自身の人生の大きな部分の終わりでもあったからなのだが。
その風貌だけでなく、聡明さや語りの上手さから、「パンク・ロックのオーソン・ウェルズ」とジェリー氏が形容する(MDCのデイヴ・ディクターも彼の自伝で同じ形容をしていた)博識トムは、ロックの百科事典だっただけではなく、ブコウスキー、バロウズ(“War All the Time”のように、やはりこの二人の作家はPIと深い関係があるのだろう)、セリーヌ、トウェイン、シェークスピアのような作家や、70年代のエクスプロイテーション映画、リチャード・プライヤーやレニー・ブルースのようなスタンダップ・コメディアンから、政治や社会のこと、日常のおもしろ話など、とにかく興味と知識の宝庫だったことが、もうその話を、考えを聞くことができない悲しさをもって回顧されている。トムは今の変わってしまったポートランドをどう思うのだろうかと。
25年以上の関係の中で、トムの最高の時も、最低の時も見てきたジェリー氏。その中でも特別の後悔をもって語られるのが、93年のPIの解散だ。ヨーロッパ・ツアー中に、トムがヘロイン切れ(先述のように、ツアー中はドラッグがうまく手に入らない)で体調は最悪、もうツアーはたくさんだ、家に帰りたいと、ツアーを途中で抜けることになり、そこでジェリー氏は激怒して、ツアー後にポートランドでラストショウをやってバンドは解散すると勝手に決めてしまった(そのライブは“Pig’s Last Stand”として音源も出た)。親友の体調のことも考えず、メンバー(ほぼ)全員が何とかドラッグを手に入れてかろうじてツアーを続けているのに、トムは逃げてしまったことに、ついカッとなってしまった。その後悔が何度も述べられている。
トムは長くコカインの売人として何とか生計を立てていたが、PI解散後はやがてそれもたち行かなくなり、家賃も滞納、家の追い出しをくらい、これまでファンジンやバンドに手紙を書いてコツコツと集めていた何千枚ものレコードを売る羽目に。トムの音楽に対する情熱を理解していたジェリー氏は、その個々のレコードの記憶にも目を配る。トムの家でパーティーをやってたときに、みんな潰れてしまって、そこである友人が、トムのコレクションからレア盤を盗んで持って行ってしまったという胸糞悪いエピソードなども挟みながら。
1992年のアルバム“Blank Blackout Vacant”の裏ジャケットにはニヒリズムの定義が書いてあるが、トムは結局そのニヒリズムに飲み込まれてしまった。そしてその裏ジャケの言葉はトムからのメッセージでもあった……。ある時、トムはジェリー氏に、「俺は無になりたい」と言ったことがあったらしい。トムを結果的にクビにしてしまい(その後再結成してからは、国内のライブやツアーにはときどき参加したり、アルバム“Latest Will & Testament”もレコーディングしているが)、そこからやや疎遠になりながら、お互いドラッグ中毒に対処しながら、お互いホームレスにもなったりしながら、最後はメサドン処方のために同じクリニックに通ったりしながら、ふたりの関係は、ある意味では予期されていたトムの死によって終わってしまう(90年代にPIのマネージャーだったDavid Wildsは、トムがドラッグで死ぬのを見たくないから辞めたのだった)。現在私たちが知るPIのあれこれを作ってきたのは間違いなくこのトムとジェリー氏のふたりであり、Thee Slayer HippyやMyrtle Ticknerといったバンドメンバーの変な名前は言葉遊びの好きなトムの案であったとか、あるファンジンのインタビューに、ふたりで相談しながらブコウスキーの引用だけで答えたという、いかにもPIらしいエピソードも語られる。
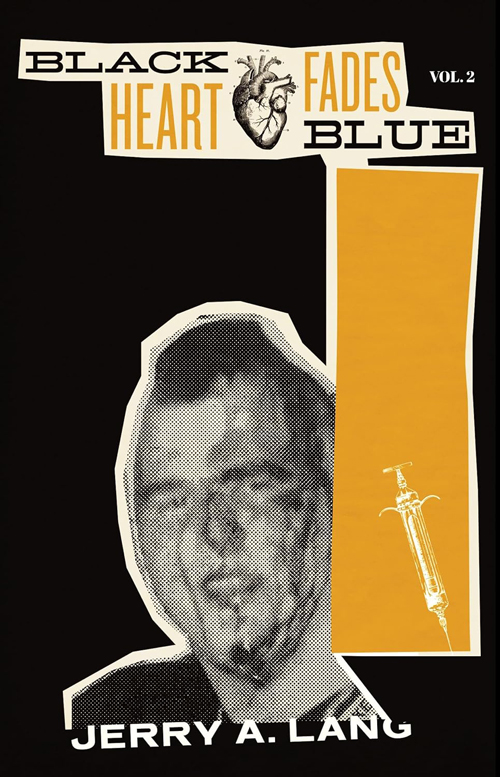
さて、そのジェリー氏である。あんなにニヒルでワルくて詩的な歌詞を書くジェリー氏がどんな人物なのかの鍵は、激しいジャンキー生活と、バンド名をボードレールの詩から取るような、隠れた(意図的に隠した?)知性を両立させるその器量にあるのではないだろうか。Poison Ideaのバンド名の元になったボードレールの“Le Poison”を読んでみると、葡萄酒と阿片について書かれたものだということがわかるが、これは正にジェリー氏そのままじゃないか! ただワルいだけではない。デカダンスと酩酊と身体的暴力をミックスさせたそのキャラクターこそが、私たちがいつもPIに惹かれてきた理由の一つだろう。ちなみに本書で紹介されるジェリー氏の文学的側面ということであれば、オスカー・ワイルドやディケンズ、TS・エリオット、ブライオン・ガイシン、サルトルやアリストテレスなどを引用したり、引用して人を驚かせたエピソードを披露したり(ジャンキーのパンクがサルトルの「蝿」の一節を暗唱するといったふうに)、その影響を語ったりしながら、ポートランドの週刊フリーペーパーに、『異形の愛』のキャサリン・ダンがエッセイを書いていたとか、本書執筆のきっかけを作ってくれた、Feral Houseのアダム・パーフリーの家でのパーティーにキャシー・アッカーがいたとか、そういった小ネタも入れてくる。
ジェリー氏もアメリカのパンクス(に限らずだろうが)によくあるように、父が暴走族のゴロツキ、母はアル中という両親が17歳のときにできた子で、ジェリー氏8歳のときに両親が別れたあとは、父が住む、大学があって進歩的なオレゴン州ユージンと、母の家族がいるモンタナ州のミズーラやディアロッジという、ホワイト・トラッシュと犯罪者だらけのど田舎を行き来しながら、弟妹の面倒をみる生活がしばらく続くという境遇の中で育っている。でも自分がこうなったことを、そういった環境のせいにはしたくない。それはあくまで自分の責任で、ドロップアウトが他の人よりも早かっただけだと、本書の中で何度も確認するように書いているから、ジェリー氏の不良っぷりは若い頃の経験のせいだと安易に推論するのは、本人の意図とは違うのかもしれない。しかし第1巻で記される幼少期の経験はどれも衝撃的で、例えば父方の家族の集まりの最中に、余興としていとことケンカすることを家族に強いられ、それがムカついて父の銃をいたずらで持ち出し、フェンスに向かって撃ったら、父親にボコボコにされる、という体験が8歳のとき。ドロップアウトする少し前、父親の当時の性悪彼女の悪口を言ったら父にひどく殴られ、その経験がそれ以降、ジェリー氏のケンカの際のダメージの“物差し”になり、酔っ払ってケンカをするのが好きだったというジェリー氏の荒れた時代のケンカ三昧の生活を、その物差しは下支えすることになる。「ボコられてもケガはそのうち治る。ボコられるよりもヒドいことは人生にはたくさんある」と何度も書いているが、それは第2巻の表紙のように、ボコってボコられた経験を数多く積んだ者だからこそ説得力を持つ言葉であろう。
PIのファン、またここまで本稿を読んだ方なら容易に想像がつくと思うが、ジェリー氏の生き様には、PI等でのバンドの活動からドラッグがらみの“死の匂い”まで、激しいアップダウンがある。ただ裏切りや本人の「暴力」(人生で3回、女性に手を上げた経験も仔細に語っている)など、自らの悪行も含めて、本書でそれらを自慢げに語るような感じでもなく、文字通り素直に、誠実に告白しているのが何ともジェリー氏らしい。
若い頃はジャームスのダービー・クラッシュの、衝動と知を両輪にして刹那的に暴走するオンボロ車のような生き方に憧れ、自分は18歳までに死ぬんだと信じ込みながら「ノー・フューチャー」の生活をしていて、父が押し付けてきた「家族」の価値観に反抗し、また実際に家庭よりもストリートの方が安全だったという境遇もあり、同じような家出少年たちと始めたのがPoison Ideaである。これは先にも書いたが、アメリカのパンク自伝ではたまに出てくる「ストリートの掟」というやつだろう。家の方が暴力やハラスメントにまみれていて、パンクの格好をしているだけで襲撃されるストリートですらまだ“安全”だったのだ。
10代半ばでポートランドのシーンに関わるようになり、最初はアート系ノーウェーブと最初期のハードコア・パンクのどちらにも顔を出して、コレクティブのようなSmegma周辺の人たちやWipersのグレッグ・セイジ、Dead Moonのフレッド・コールなどの影響を受け、面倒を見てもらいながら、PIを始めて自分のやりたかったことを実現していく。“Feel the Darkness”が、娼婦になった友人女性がシリアルキラーに殺された物語を語るように、そういったストリートでの経験に基づいた曲を書き歌うことで自らの精神を何とか保ち、火を噴いたり自傷したりといったステージで見せる過激なパフォーマンスもまた、自分の辛い経験を身体の外に放出するセラピーのようなものであった。
そんな我々凡人の想像も及ばないようなハチャメチャな人生を歩んできたジェリー氏にも、本書の終盤ではドラマチックな出会いがあったことが明かされ、ようやく「安定」を手に入れつつあり、この自伝は「ハッピーエンドの遺書」として、生きることへの希望を見出して一旦閉じられる。
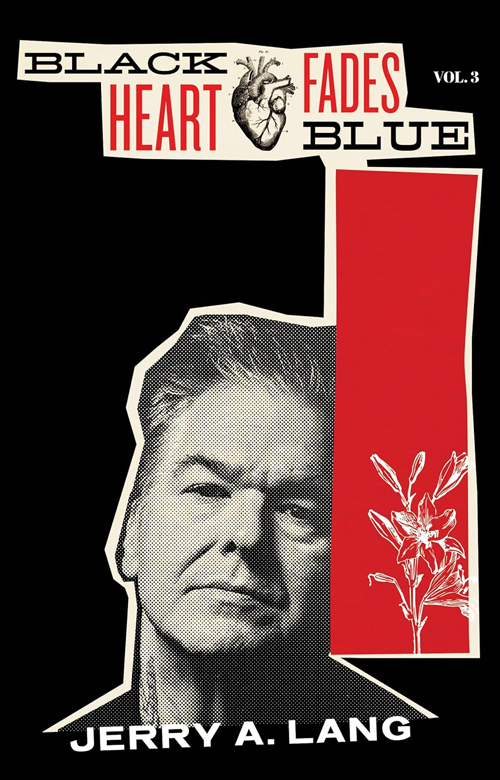
相変わらず書評というよりは本の紹介に始終してしまっているが、できるだけたくさんの人がこの本を買って読んだらいいなと思いながらここまで書いてきた。が、果たしてこの本の和訳は出るのだろうか。長尺、おまけに目次も章題もなければ写真もない無骨さ、そして何よりアメリカ特有とも言えるドラッグ問題の話が多すぎるし、Poison Ideaは日本盤CDは何度か出たものの、何千人も客を呼ぶメジャーのバンドではなかった。バンドとしてのPIのことを知りたいのであれば、先述のドキュメンタリー映画“Legacy of Dysfunction”の方が適しているかもしれない(あの映画はジェリー氏がバンドの遍歴を語りながら進んでいくので、この自伝の概要版とも言えそうで、重複する内容ももちろんあるし、何より映像なので、PIはもちろんのこと、ジェリー氏がPI以前にやっていたSmegma(映画の制作がそもそもSmegma StudiosのMike Lastraだ)、The KineticsやThe Standといったバンドのレアな映像も少しだが見られる)。この映画も含めて、大企業ディスクユニオン様あたりが先の個人情報漏洩のお詫びも兼ねて、採算度外視で頑張って出してくれたらとも思うが……。
何にせよ、当レーベルのような新刊を2年以上も出せていない弱小出版社には荷が重すぎるのは明らかなので、こうして書評で紹介することにした。が、紹介したのはほんの少し、当然膨大なエピソードがここには書かれている。オレゴンのゲイ差別法案に反対するライブにNirvanaと、Mudhoneyがキャンセルの代わりにHelmetとPIの3バンドで出て、カート・コバーンのような人には普通に話せる友人が必要だった、3回だけ言葉を交わしたことはあるが、あるいは自分がその友人になれたかもしれない、とカートへの配慮を見せたり、パスヘッドに用意してもらったメタリカのライブのチケットとバックステージパスを、気が変わって会場周辺にいたキッズに売ったり、オーストラリアでHard-Onsとドラッグ三昧の日々を送ったり、MotörheadのギターだったワーゼルがPIに加入したいと何度も連絡してきたのをなんとか断ったり、Elasticaがポートランドに来たときに、レコードにサインをしてもらおうと長い列に並んでたら、予期せぬトラブルが起きてそのレコードを捨てたり、“Feel the Darkness”などのアルバムに「プロデューサー」として勝手に名前を載せたドラムのSlayer Hippyを痛烈に皮肉ったり、ポルノ・アーケードでの労働の話だったり……。
名作詞家ジェリー氏の言葉のチョイスはこの本でもかなり考え抜かれ、冴えており、これまで目にしたことのない単語や慣用句が次々と出てくるので、辞書を引き続けないと話がまるでわからない部分もあったし、正直よくわからないままの部分もある。それでも、英語の本なんて読んだことないけど……という人にも、この「黒いハートは鬱気を覆う」とでも訳せるタイトルの本書をおすすめしたい理由は、この本がハードコア・パンクの何たるかを体現してきた、ジェリー氏のアティチュードそのものだからである。それはつまり、自分の責任は自分で取ること。その覚悟とそれを裏打ちする経験が、この600ページには仔細に刻まれているのだ。
第2版からはこの全3巻が1冊にまとめられて出版されるらしいが、この本が世界中で売れまくって、ジェリー氏の物語がさらに本人の手から紡がれることを待ちたい。
◆
https://rarebirdlit.com/black-heart-fades-blue-signed-by-jerry-a-lang/
https://poisonidea.bigcartel.com/
https://americanleatherrecords.bigcartel.com/
付記:
この駄文が機能してほしいことがひとつ。2004年の来日時に、ジェリー氏に可愛い便箋に日本語で書かれた手紙をあげた女性がいたそうで、その後ジェリー氏は住所をなくしてしまって返事が書けなかったと本書で弁解していたので、もし、万が一その手紙の方がこれを読んでいたら、そういうことだそうです。
その他の書評
