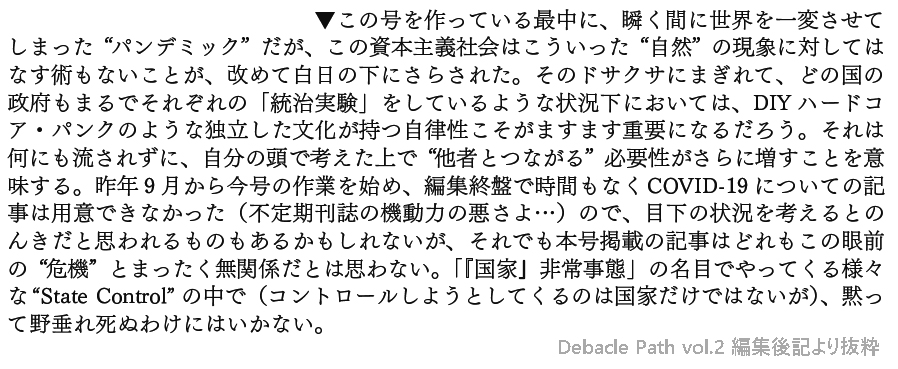鈴木が2012年からつけていたブログのサーバがついに死んだらしく、データにもアクセスできない状態となってしまったそうなので、オンライン上に残っているものを漸次下記リンク(メニューのAboutにもリンクあり)に残しておきます。
【書評】Hard-Core: Life of My Own / Harley Flanagan
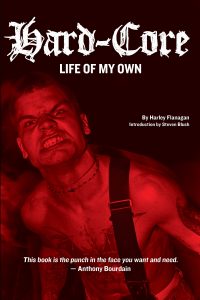
【書評】
Hard-Core: Life of My Own / Harley Flanagan(Feral House, 2016)
/鈴木 智士(Gray Window Press)
ちょうど1年前に、「“Cro-Mags”の名称を誰が使うか問題」に決着がついた、という出来事もあったが、アメリカン・ハードコアの歴史の中で、Cro-Magsのメンバーほど「お騒がせ」な人たちもいないだろう。80年代中盤の結成時から、メンバーは出たり入ったり替わったり、その後は様々なバンド名でCro-Magsの(特に1stアルバムの)曲を演奏し、一体何が「本物」なのかと聞く側は混乱した。ただバンドのオリジナル・メンバーであり、ベース(と時にはヴォーカル)を担当してきたハーレー・フラナガン氏によるこの自伝は、その数々の「お騒がせ」のディテールを知る前に、その幼少期にまず驚かされる。
父はネイティブ・アメリカンの血も入っていたという強盗・サギ師・犯罪者。アメリカの西と東を行き来し、マンソン・ファミリーにスパーンランチに連れて行かれそうになったというヒッピーだった母は、「奇人」ハリー・スミスに“Rosebud”という名前で呼ばれ、ハリー・スミスの「精神的な妻」であったという(この点は先日『ハリー・スミスは語る』を出版されたカンパニー社さんからtwitter上で教えていただいた)。そんな両親はハリー・スミスを通して知り合ったが、ハーレーが生まれてすぐに父は姿を消し、母は幼いハーレーを連れてアメリカ中を、そしてヨーロッパをヒッチハイクで生活するようになる。やがて母はデンマークでドラッグの売人の男と付き合い始め、2人はデンマークに住み着き、有名なクリスチャニアを含め様々なコミューンを渡り歩いたらしい。「フリーラブ」の世界で誰彼かまわずセックスする親たち世代を見て、ハーレーのような子どもたちは思春期を迎える前にアルコール、ドラッグ、セックスを覚えたというから、やはりデンマークという国が現在もおかしい(褒め言葉)のはこういうところに根があるのかもしれない。
6歳の頃にデンマークのアート偏重フリースクールでドラムを覚え、その後家族はモロッコに数ヶ月住み、そこでハーレーが書いた絵と短編は、その2年後、ハーレー9歳のときにアレン・ギンズバーグの序文付きで出版されている。母や後にStimulatorsで一緒にバンドをやる叔母のDenisはギンズバーグと近く(叔母はニューヨークで他にリチャード・ヘルやらと一緒に住んでいたこともあった)、この頃ハレー・クリシュナの始祖プラブパーダと親交があったギンズバーグから、ハーレーは瞑想を教わったとも書いている。
ハーレーの初のパンク・ショウは1977年頃のデンマークで、Lost Kids、Sods、Brats(後のMercyful Fate)などを見て、78年には叔母に連れられてイギリスにも行き、「死ぬ前」のオリジナル・パンクを体験してもいる。その後79年に母子はニューヨークに戻り、当時はプエルトリコ人ギャングと黒人ギャングの抗争の場であったマンハッタンのゲットー、ローワーイーストサイド(LES)に移り住む。
と、この時点でハーレーの早熟ぶりとその環境の特異さにまず驚愕する。10歳にもならないうちにパンクに出会う人はこの世代だったら珍しくはないだろうが、身近にビート・ジェネレーションを代表する詩人がおり、またパンクバンドをやっている身内の女性がいたというのはあまり聞くことのないシチュエーションだ。その後はご存知のように12歳でStimulatorsのドラムを叩き始めるが、1979年2月のシド・ヴィシャスの死により、ニューヨークのパンク・ロックは死んだとハーレー自身も把握しているように、Stimulatorsは(先月末に出たEl Zine vol.42にヴォーカルのスクリーミング・マッド・ジョージ氏のとても面白いインタビューが載っていた)The Mad、Bad Brainsらとともに、NYCのパンクからハードコアへ移行する過程の架け橋のようなバンドとなっていく。CBGBとともに、Max’s Kansas Cityというクラブでパンクのライブが行われていた時代の話だ。続きを読む →
メディア掲載情報
【Debacle Path vol.2】
「図書新聞」2020年5月9日号(3447号)掲載の、文芸評論家の岡和田晃氏の連載、「〈世界内戦〉下の文芸時評」第63回で、Debacle Path vol.2のジェフ・エヴァンス、マックス・ウォードとのインタビューについて少し触れてもらっています。
ジェフとのインタビューにも出てきますが、岡和田氏は以前Skavenについて、「トーキングヘッズ叢書(TH、アトリエサード)」にRPGゲームの側面から面白い記事を書かれているので、本インタビューを読まれた方はそちらもぜひ読んでみてください。
今日(新宿で現在唯一やってる本屋の)模索舎で買いましたが、図書新聞の最新号に、Debacle Path vol.2について批評家の岡和田晃氏の連載「〈世界内戦〉下の文芸時評」第63回で、少し触れてもらってます。 pic.twitter.com/AtGfBOCPpN
— Gray Window Press / Satoshi Suzuki (@graywindowpress) May 2, 2020
“I Don’t Want a Punk Generation”: Punks in Istanbul
“I Don’t Want a Punk Generation”: Punks in Istanbul
By Elif Erdogan
Although the world had its own punk scene in 1970s, Turkey had political turmoil that prevented people from having their own punk movement around that time. Istanbul, where Turkish punk can be most prominently seen, has been a house of chaos for holding two very opposite concepts as its own nature. As a cliche, it is the middle-ground for Asia (Anatolia) and Europe, but this city is also the battle ground for rich and poor, conservatives and progressives, right-wing and left-wing activists.
I happen to witness Gezi Parkı Protests when I was 13 years old, which influenced my political behaviour. I was already influenced by punk’s political messages, but it was the first time that Turkish punk rock had an effect on me. Although, Turkish demonstration music bands created a lot of songs influenced by Gezi Parkı Protests, Cemiyette Pişiyorum’s Buldozer (POMA) was not romanticizing the protests, but showing the resistance of people against power. Despite the fact that I left Istanbul at the age of 18 to live in Nagoya, I am still following Turkish punk scene constantly and it is more active than it used to be. But it was not always like that.
Turkey did not have a punk scene when other countries were writing their own history around 1980s. “I don’t want a punk generation” were the words of Kenan Evren who started the 1980’s Coup D’etat and traumatized every Turkish citizen. It was a period of time when soldiers would enter your house without your permission, to search your library whether you own books related to politics. Many artists or intellectuals continued their life in other places like Europe or America to carry on their work. People started to burn their music records and books so that they would not be arrested by the soldiers. Therefore listening to songs about anarchy would be the last thing a civilian would like to do in Turkey. Thus, Turkey didn’t have a solid punk generation in 1980s when it was booming in other parts of the world.
続きを読む →
【Debacle Path vol.2】小特集「ハードコア・パンクと学術」について
Debacle Path vol.2の発売日、4月23日も近づいてきたので、少し中身の宣伝というか、今号の小特集の制作意図、というと大げさか、補足説明を書きました。以下参考にしていただければ嬉しいです。
■取扱店(随時更新)
(前にもツイッターに書きましたが、レコード屋・小売書店等も目下のコロナ禍で営業自粛したりと大変な状況なので、どうぞこういったお店で買っていただければ)
今回の小特集「ハードコア・パンクと学術」は、パンクスがパンク文化を通して「学んだ」先には何があるかを考えるために、その一例として、アカデミア(大学などでの学術研究)に進んだアメリカの3人のパンクスにインタビューをしたものだ。中身は本号を読んでもらうとして、なぜこの3人にインタビューしたのかは特に誌面にも書いていないので、ここで説明しておこうと思う。
世界中どこにでも簡単につながる「小さな」DIYパンクシーンなので当然と言えば当然だが、今回インタビューした3人と私はもちろん、3人の中でもつながりがあり、Asunder(2006年のCorruptedとの日本ツアーでライブを見た人はラッキーでした。あんなにすべてがかっこいいバンドはそうそういない)のジェフ・エヴァンスと625マックス・ウォードは、90年代後半にオークランドのコミュニティ・カレッジで一緒に日本語を勉強していたり、スチュアート・シュレイダーと当レーベルの共同運営者・AKアコスタは、ニューヨーク大学大学院時代の知り合いで(AKはマックスとも同大学院時代からの友人で、日本では早稲田の某ゼミで一緒だった)、といった感じで、アカデミアで知り合って、「ああ、あなたもパンクだったんだ」とそこで判明する、というような出会いをしている。私自身はジェフとはそのCorruptedの日本ツアーのときに仲良くなり(今はなき岐阜51でのライブの打ち上げで、小津安二郎の話をずっとしていた覚えがある)、以降連絡を取り続け、私がアメリカに行くときはオークランドなどで会って、一度は古本屋巡りに連れていってもらったこともあった。
625マックスはもう説明不要でしょう。私が20歳の頃にやっていたバンドの7インチも出してくれたように、625 Thrashcoreは世界中のファストコア、スラッシュコア、グラインドなど、とにかく「速い」バンドの登竜門のようなレーベルだった。パンクと学術生活をなるべく分けているマックスなので、今回のインタビューでは話がいろいろな方向に飛び、マックスのパンク的生い立ちから、パワーバイオレンスとは何だったのかという回顧、学術生活への道から現代アメリカ、日本をどう見ているかまで、トータル24,000字超えとかなりのボリュームになったが、彼の回答はどれも冷静で、あくまで「パンクスとしてその時々の状況で何ができるのか」が最優先されている。また日本の戦前の「思想警察」についての彼の初の著書についても語ってもらった。
スチュアート・シュレイダーは彼のレーベル、Game of the ArseholesがDiscloseやContrast Attitudeを出していたりと、2000年代前半にその名を聞いた人も多いはずだ。まったく追いきれてないが、過去にAnti-Cimexについて物凄く細かい分析をしていたこともあったと記憶している。彼がこれまでに書いたテキストは膨大な量で、それだけで本を数冊出せるような「パンク学者」だ。今回はインターネット、ソーシャルメディアによって変わってしまったDIYパンク文化は今後どうなるのか、という点なども交えながら、Disclose川上さんとの話や、彼のアカデミック著書についても話してもらった。
また付録として、インタビュー内でもたびたび言及される、アメリカの民主党を「変えつつ」ある、DSA(アメリカ民主社会主義者)についての簡単な解説をAKアコスタが書いた。
と、Debacle Pathはあくまで私個人がAKアコスタの力も借りながら勝手に作っているハードコア・パンクの「個人誌」のようなものでもあるので、寄稿やインタビューをお願いするのも必然的に友人知人となる。今回もそれは変わっていないし、今後もおそらく変わらないだろう。以前にも書いたが、DIYパンクの醍醐味はこの距離感の「なさ」にある。みんな同じ地平にいるのだ。
昨今アメリカのパンクバンドがかなり頻繁に来日するようになったが、あまり具体的なところまでは踏み込んで語られることのないそういったバンドが持つ政治観も、このインタビューや付録を読んでもらえれば、おそらく概要程度は掴めるのではないかと思う。インタビュー中でも触れられているが、アメリカのラディカル・ポリティクスは、私が2000年代の始めから固定観念のように持っていたもの―行動的なアナキズムが根底にあるもの―とはかなり変わり、特に2016年からの「トランプ以降」は大きな変動期にあるようで、この状況は特にアンダーグラウンドで活動している現行のバンドには大きな影響を与えているはずだ。
小特集以外の記事―連載エッセイやインタビューの続き、イタリア・トリノからのスクワットの報告やイスタンブールのパンク史などなど―はここではいちいち説明しても仕方がないので、ぜひ読んでいただければと思う。
新型コロナウイルス禍により、この数ヶ月で世界は変わってしまったが、そのことについては編集後記で触れた。以下に該当部分だけ抜粋し掲載しておく。こういった「非常時」だからこそ、DIYハードコア・パンクの文化はその真価が問われることになるだろう。その一助として、Debacle Pathが機能すれば幸いだ。