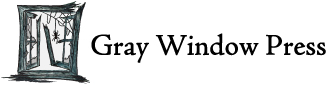Debacle Pathの「別冊」を始めました。

別冊第1号『ハードコア・パンクの歌詞を読む』は、主にハードコア・パンクのバンドの曲の歌詞を読んで書かれた33のレビュー・解説を集めた冊子です。
ハードコア・パンク取り扱いの小売レコード店、書店、ディストロでは10/13発売予定。
直販も10/13ごろの発送になります。予約受付中。

■ハードコア・パンクの歌詞を読む ―Debacle Path 別冊1
A5判 並製 64ページ
日本語
600円+税
発売日:2020年10月14日
ISBN978-4-9910725-3-6
ハードコア・パンクのバンドはそれぞれの時代に、何をどのように歌ってきたのか。誰もが知っているクラシック・バンドから「今」を伝える現行バンドまで、1曲1曲の歌詞を読み込んで書かれた33のレビューを掲載した、Debacle Pathの「別冊」第1号、全64ページ!
掲載バンド:Alement, Antischism, Body Pressure, Born Against, Corvo, Dagger, Daily Ritual, Dirt, Dystopia, Extended Hell, Final Conflict, Grief, Hibernation, HIRS, Industrial Suicide, The Insane, Insolent Wretch, Instant Agony, Instinct of Survival, Living World, Los Crudos, MDC, Namatay Sa Ingay, Pg.99, PMS 84, Poison Idea, Protestera, 7 Minutes of Nausea, Sore Throat, Special Interest, Unhinged, Violators/ CrimethInc.(レーベル)など
歌詞のテーマ:反警察、反資本主義、反レイシズム、反セクシズム、アナキズム、Black Lives Matter、反テクノロジー、反監獄、フェミニズム、プロチョイス、戦争責任、植民地主義、疑似民主主義、アメリカの覇権、監視社会、性的マイノリティ、ジェントリフィケーション、反音楽、ニヒリズム、ディストピア、移民、ナチズム、反宗教、KKK、動物の権利、菜食主義、暴動、暴力、厭世、セルアウトなど
寄稿者:
Eriko(M.A.Z.E.)
久保 景(Deformed Existence)
黒杉 研而(ATF, Deformed Existence)
コウヘイ(Rashomon, 鏡)
Terroreye(Kaltbruching Acideath)
山路 健二(EL ZINE)
渡邉(MATERIALO DISKO)
A.K.アコスタ
鈴木 智士
※一般書店、オンライン書店への流通は11月以降を予定しています。